目次
NOAHプロジェクトでは以前より「AI分野への進出」を掲げていますが、公式発表以外の情報や具体的な連携については、現時点でははっきりと確認できていません。
ですが、AI技術とブロックチェーンの融合が多方面で盛り上がりを見せていることは事実です。
今回、プラチナム社の公式YouTubeチャンネル「Ai Agents LaunchPad by Palo Alto Ai Research Lab」において、「AI + Web3: 金融とコンテンツ作成の未来がここに」というテーマの動画が公開されました。
今回本記事でお伝えする情報はあくまで参考資料として動画の内容にも触れるものであり、動画全体の内容と完全に一致するわけではありません。
ここからは、上記の動画をはじめとするAIとWeb3の融合にまつわる話題をベースにしつつ、特に注目したい5つのポイントを中心に解説していきます。いずれも、ブロックチェーンや仮想通貨市場の今後を考えるうえで見逃せない要素と言えるでしょう。
※今回のブログ記事の情報源:プラチナム社公式youtubeチャンネル(Ai Agents LaunchPad by Palo Alto Ai Research Lab)
AI + Web3: 金融とコンテンツ作成の未来がここに
分散型AIとコンテンツ制作の革新
中央集権型から分散型へ
近年、AI技術を活用したコンテンツ制作は急速に発展しています。たとえば、画像生成AIや自然言語処理モデル(GPT系統など)を使った記事作成、動画生成など、クリエイティブの自動化や効率化が進む一方、一般的に利用されてきたAIプラットフォームの多くは中央集権的な構造を持っていました。つまり、大規模クラウドサーバーや特定企業の管理するデータセンターを中心として学習・推論が行われ、ユーザーはそれらのサービスにアクセスするという形です。
今回の動画で取り上げられていたプロジェクトは、こうした「中央集権型AI」の限界や課題を解決する手段として分散型AIの概念を打ち出しています。ブロックチェーンやWeb3の考え方と非常に相性が良いため、ユーザー自身がネットワークに参加しながらAIの性能を高めていく仕組みを実現できる点が大きな特徴です。
クリエイターが主役となる新たな制作プロセス
分散型AIにおいては、大手プラットフォームや企業のサーバーに頼らず、多くの参加者が持ち寄るコンピュータ資源(GPUなど)を使ってモデルを学習・改良し続けます。クリエイターはAIに対してフィードバックを与えながら、自身が作りたい作品のスタイルや特徴を学習させることが可能です。こうした形で進化したAIは、それぞれのクリエイターの意図をより正確に反映したコンテンツを生み出すため、制作における柔軟性と独自性が飛躍的に高まるとされています。
また、Web3の技術と組み合わせることで、どのユーザーがどのようにAIの学習へ貢献したかが明確化しやすくなり、貢献度に応じた報酬の分配も透明性を持って行われます。たとえば、自身の画風やキャラクター設定を提供したクリエイターが、作品の生成プロセスを通じて得られる収益の一部を受け取るといった仕組みが考えられます。このように、**「みんなでAIを育てる→育てた成果をみんなでシェアする」**という循環が形成されるわけです。
ユーザー主導のAIモデル
フェデレーテッドラーニングの導入
動画の中で特に強調されていたのが、フェデレーテッドラーニングという技術です。通常の機械学習では、大量の生データを中央サーバーに集約してモデルを学習させます。しかしフェデレーテッドラーニングの場合、ユーザー側の端末(PCやGPUサーバー)でローカルに学習を行い、その学習結果であるパラメータのみを収集・統合して最終的なモデルを更新します。これにより、次のような利点が得られます。
- プライバシー保護
ユーザーのローカル環境にある生データは外部に出さないため、センシティブな情報を守りつつ学習を進められる。 - リソースの有効活用
大企業が運営する大規模クラウドサーバーだけでなく、世界中に散らばる個人や団体が所有するGPUリソースを合わせて活用できる。 - コミュニティ主導の進化
コミュニティに参加するユーザーが多ければ多いほど学習効率が高まり、短期間で高度なモデルへと成長しやすい。
これらの仕組みによって、AI開発の「独占構造」を打破し、より多くの人々が公平に参加できるプラットフォームが形成されるのです。特に、ブロックチェーンの分散型ネットワークと組み合わせれば、パラメータ更新の履歴をチェーン上に記録するなど、学習プロセスの透明性を高めることも期待できます。
クリエイターと一般ユーザーの垣根がなくなる可能性
また、フェデレーテッドラーニングの導入は、クリエイターだけでなく一般ユーザーもAI開発に携われるという点で大きなインパクトをもたらします。たとえば、普段はただ作品を見るだけのファンが、自分のPCやスマートフォンを使ってAIの学習を手伝うといったケースです。ファンの視点や嗜好がモデルに反映されれば、より多面的でユニークな作品が生まれる可能性が高まりますし、その貢献が報酬やトークンといった形で還元される仕組みが整えば、作品とファンとの結びつきがさらに深まるでしょう。
こうした動きは、「ファン参加型の創作コミュニティ」という新たなエコシステムを築く基盤となり得ます。クリエイター、ファン、そして技術者が互いに協力してAIモデルを磨き上げ、それぞれが自分の得意分野を活かして価値を生み出し合う――まさに、Web3時代のクリエイティブ・エコシステムを象徴する動きと言えるかもしれません。
収益化と市場展開
広告挿入や特許技術による収益モデル
動画で解説されていたプロジェクトの一つでは、ユーザーが作成したショートアニメや動画コンテンツに対し、自動的に広告を挿入してマネタイズする特許技術を活用する事例が紹介されていました。これは、ユーザーがクリエイトしたコンテンツと、広告やスポンサーシップ情報を違和感なく融合させる技術をAIが担うというものです。
従来、広告モデルと言えばプラットフォーム(YouTubeやSNSなど)のアルゴリズムに制御され、制作者側が収益を十分に得られないケースも少なくありませんでした。しかし、分散型AIとブロックチェーンの仕組みを組み合わせることで、コンテンツ制作の報酬配分をクリエイター主導で決定することが可能になり、プラットフォーム手数料の削減や、透明性の高い利益分配が実現しやすくなるのです。
DeFiプロトコルとの連携
さらに、ブロックチェーン界隈で盛り上がりを見せている分散型金融(DeFi)と組み合わせることで、収益化の可能性は一段と広がります。動画での詳細説明は後述されていましたが、たとえば広告収益やトークン販売で得られた資金をDeFiの運用に回し、コミュニティ参加者へリワードを還元するモデルなどが考えられます。
- NFT化やロイヤリティ設定
クリエイターが作品をNFTとして発行し、二次流通での取引が行われるたびにロイヤリティを受け取る。 - DeFi運用による利回り分配
作品や広告収益から得たトークンを、ブロックチェーン上の流動性プールやステーキングに活用し、得られた利回りをコミュニティ全体に分配する。 - 協力者へのインセンティブ
AI学習に参加したユーザーや、作品の宣伝を手伝ったコミュニティメンバーに対して、トークンや特別な権利を付与する。
このように、AI技術がコンテンツを生み出し、そのコンテンツをブロックチェーンで管理・流通・収益化するという流れが確立すれば、これまでの中央集権的なビジネスモデルにはない自由度と公平性が実現されるでしょう。投資家やホルダーのみならず、一般ユーザーやクリエイター自身にも新たな収益機会や価値交換の仕組みがもたらされるのです。
対象顧客と市場の可能性
ここまでプラチナム公式YouTube(AI + Web3: 金融とコンテンツ作成の未来がここに)の動画に登場したAIプロジェクトの概要や、そのコンテンツ生成・収益化モデルについて触れてきました。こうした分散型AIやWeb3の仕組みが、実際にはどのような層や業界に受け入れられるのかを考えることで、将来的な市場規模やビジネスチャンスをより明確にイメージすることができます。
1. クリエイターとインフルエンサー
まず見逃せないのが、SNSや動画配信サービスを中心に活動しているクリエイター、あるいはインフルエンサーと呼ばれる人々です。
彼らは日々、膨大なコンテンツを生み出してフォロワーを獲得し、広告収入やグッズ販売などで収益を上げています。しかし、多くの場合はプラットフォームのアルゴリズムや規約に縛られ、自らのブランディングやファンコミュニティを自由に展開しきれないというジレンマを抱えていました。
分散型AIとブロックチェーンを組み合わせたプラットフォームでは、クリエイターが主導権を取り戻し、自身の作品や広告の出稿方法、収益配分などをより自由に設計できるようになります。特に、前半で紹介した自動広告挿入や特許技術を活用すれば、作品世界観を壊さない形でマネタイズしながら、コミュニティと直接的につながる仕組みを作れるでしょう。こうした利点は、クリエイターやインフルエンサー層にとって非常に魅力的です。
2. 広告主やマーケター
次に注目すべきは、広告を出稿したい企業やマーケターです。
従来、企業がSNSや動画サイトに広告を掲載する場合、その広告枠やターゲット設定はプラットフォーム側のルールや枠組みに則らなければなりませんでした。さらに、ユーザーの個人情報を広告配信に活用する際のプライバシー問題や規制強化も年々厳しくなっています。
分散型AIを活用したプラットフォームでは、ユーザーが自分のデータや嗜好をコントロールしながら、必要に応じて広告モデルに参加することが可能です。たとえば、自分の視聴傾向や好きなコンテンツジャンルを提示する代わりに、広告ビューイングやコンテンツ共有による報酬を得る仕組みが考えられます。企業やマーケターにとっては、ユーザーの同意を得たうえで精度の高いターゲティングができるため、広告効果とユーザー体験の両立が期待できるわけです。
3. ゲーム・アニメ・エンターテイメント業界
また、ゲーム・アニメ・エンターテイメント業界全般にも大きな可能性があります。
もともとクリエイティブな要素とファンコミュニティの結びつきが強いセクターであり、そこに分散型AIの仕組みを取り入れることで、**「ユーザー参加型」かつ「トークンエコノミーによる報酬」**が発生する新たなビジネスモデルを構築しやすいからです。
- ゲーム内アイテムやキャラクターをAIが生成し、ユーザーが所有権を得る
- アニメ制作の一部工程をAIが担い、ファンが設定協力やデザイン提案で報酬を得る
など、既存の枠組みを超えた発想が多々生まれています。これは前半の記事で言及した「フェデレーテッドラーニング」や「コンテキスト技術」などが活きてくる領域でもあり、今後市場が拡大することは間違いありません。
4. 企業や投資家(B2B/B2C両面)
最後に、企業や投資家層へのアプローチも見逃せません。
上述のクリエイター・広告主・エンタメ業界などに向けて、分散型AIサービスを提供する企業が増えれば、B2Bビジネスとしても大きな収益チャンスが生まれます。さらに、投資家にとっては、技術や市場ポテンシャルに魅力を感じるプロジェクトへと資金を投じ、その成長を期待する道が広がります。
ブロックチェーンのトークンエコノミーと絡めれば、小口投資家がプロジェクトの初期段階から参加することも容易であり、スタートアップへの出資形態が多様化する可能性も大いにあるでしょう。
金融サービスとしてのQuintesの役割
動画の後半で登場した「Quintes」は、シャリア(イスラム法)準拠の分散型金融(DeFi)プロトコルとして紹介され、非常に興味深い存在感を放っていました。前半記事では収益化モデルの一端として触れただけでしたが、ここではQuintesが具体的にどのような価値を提供するのかを整理してみたいと思います。
1. シャリア準拠がもたらすグローバルな信用
イスラム金融には、利子の禁止や投機的取引の制限など特有の倫理観が存在します。
Quintesはこれらの原則を尊重しながら、仮想通貨やトークンを資産運用に活用する仕組みを構築しており、国際特許の取得や複数の研究機関からの検証も受けています。こうした**「シャリア準拠」**の仕組みは、中東をはじめとするイスラム圏だけでなく、グローバル市場全体においても「公正な金融プラットフォーム」としての評価を高める要因となり得ます。
さらに、シャリア適合性はリスク管理の面でも効果的です。過度なレバレッジ取引や投機的な金融商品を排除し、透明性と安定性を重視することで、一定の安全域を保ちながら投資家の資産を保全する仕組みを整えやすくなります。これは「AIとDeFiの融合」による新種のリスク(アルゴリズムの暴走など)を抑えるうえでも、大きなメリットがあるでしょう。
2. 安定した利回りを実現するクリプトノミクス
Quintesが注目されるもう一つの理由は、独自の「クリプトノミクス(トークン経済設計)」によって、比較的安定した利回りを提供しようとしている点です。
現在の仮想通貨市場は価格変動が激しく、一般投資家にとっては資産のボラティリティが大きなリスクとなっています。Quintesは、複数の特許技術やシャリア準拠のトレーディング戦略を駆使し、
- 過度な投機を避けながらも、堅実に資産を増やす
- ユーザーが自分の仮想通貨を預けるだけで、自動的に複利運用が行われる
といった仕組みを目指しているとのこと。
DeFiを利用する際の一般的な課題として、運営チームの信頼性やハッキングリスクなどが挙げられますが、Quintesはオフチェーンカストディとオンチェーン・スマートコントラクトのハイブリッド運用によって安全性を高めるなど、多層的なセキュリティ対策を講じています。これらがうまく機能すれば、ユーザーが**「安心して預けられるDeFiプラットフォーム」**として地位を築く可能性も十分にあるでしょう。
3. AI・Web3とのシナジー
Quintesのようなシャリア準拠のDeFiプロトコルは、分散型AIやWeb3プロジェクトと組み合わせることでさらなるシナジーを生み出します。
たとえば、分散型AIを使って投資判断やリスク管理のアルゴリズムを最適化することで、Quintesの運用効率が向上するだけでなく、投資家にもわかりやすい形で「AIによる透明性の高い運用プロセス」を提示できるかもしれません。
また、Web3のトークンエコノミーと組み合わせて、AIプロジェクトやクリエイターコミュニティがQuintes経由で資金調達を行い、得られたリターンをコミュニティに還元するような仕組みも考えられます。
まとめと今後への期待 〜NOAHプロジェクトとの可能性を踏まえて〜
今回のご紹介した「AI + Web3: 金融とコンテンツ作成の未来がここに」というプラチナム公式YouTube動画の内容は、分散型AIとDeFiという2つの領域が交錯することで生まれる新しい可能性をわかりやすく示したものでした。特に、クリエイター主体のコンテンツ制作やフェデレーテッドラーニングを活用したAI開発、シャリア準拠の安定的なDeFiプラットフォームが同時に進行している点は、これからの仮想通貨・ブロックチェーン市場を考えるうえで大きなキーワードとなるでしょう。
NOAHプロジェクトでも「AI分野への進出」が示唆されており、もし今回のような分散型AIプロジェクトやシャリア準拠の金融サービスとの連携が実現すれば、双方の強みを活かした新たなエコシステムの構築が期待できます。現時点では公式に発表されているわけではありませんが、過去の課題を乗り越えて再起を目指すNOAHにとって、AIとDeFiの潮流は見逃せないチャンスと言えるでしょう。
仮にNOAHプロジェクトが今後、QuintesのようなDeFiプラットフォームと協力しながらAI技術を取り入れることで、投資家やホルダーが受け取るメリットが一層高まる可能性もあります。コミュニティが支持し合い、透明性の高い情報共有と収益分配が確立すれば、ブロックチェーンが描く未来をより具体的に、そして身近に感じられる日が近づくのではないでしょうか。
今後も「リコ社長のNOAH CITY ブログ」では、NOAHプロジェクトやプラチナム社、そしてブロックチェーン・AI業界の最新動向を追い続け、皆様にお伝えしてまいります。これからも新しい情報をキャッチしながら、時代をリードする技術やサービスの進化を一緒に見届けていきましょう。最後までお読みいただき、ありがとうございました!
ブログ内関連記事
リコ社長を支援してください
いつも『リコ社長の NOAH CITYブログ』をご覧いただき、本当にありがとうございます! このブログの情報が皆さまのお役に立てているなら、とても嬉しく思います。
ブログ運営やインフルエンサー活動を続けるために経費がかかっております。情報発信を継続するためには、皆さまの温かいご支援が大きな励みになります。
もし「応援したい!」と感じていただけましたら、最小1000円からAmazonギフト券でのサポートが可能です。ぜひご検討いただけますと幸いです!

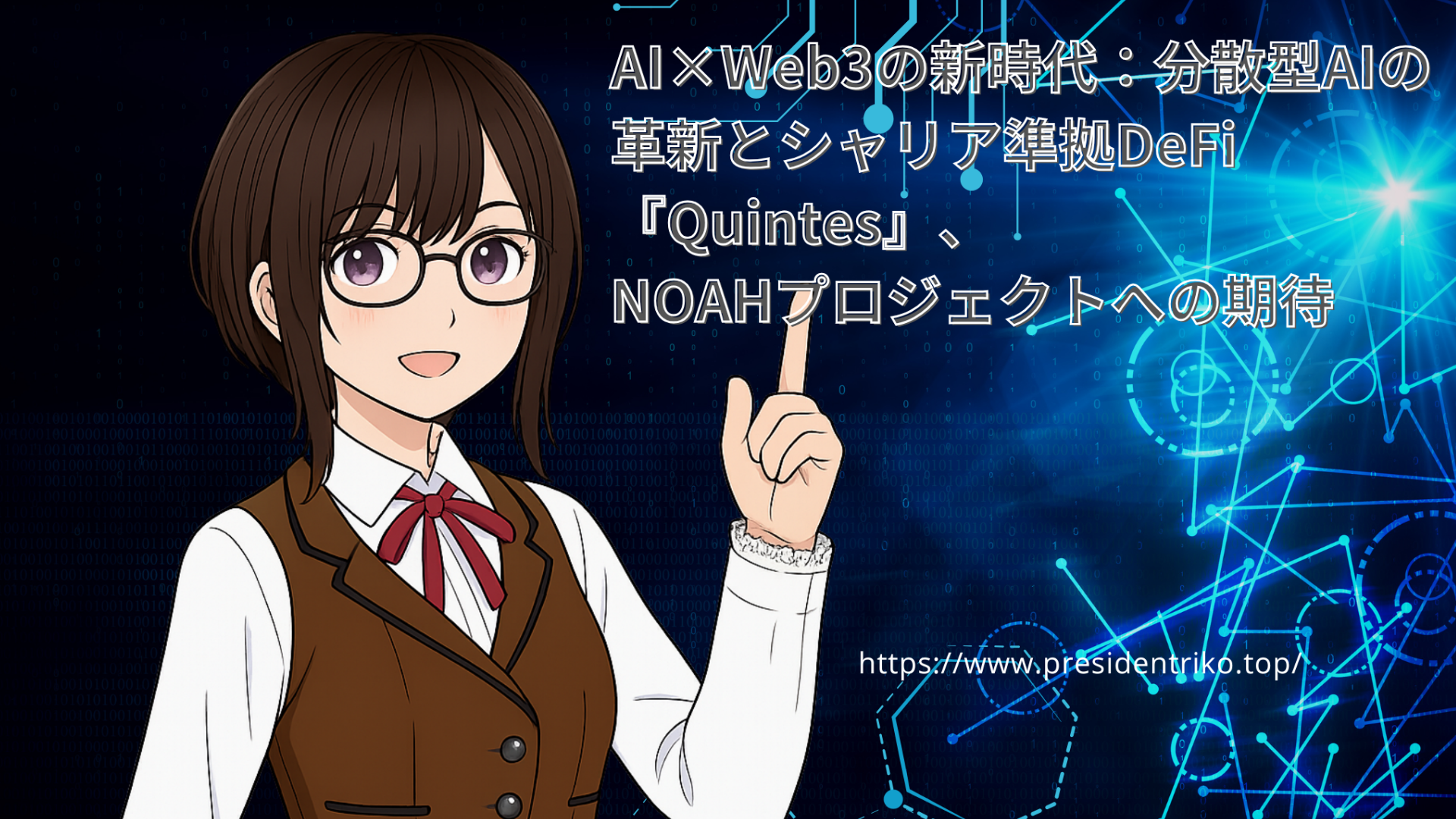





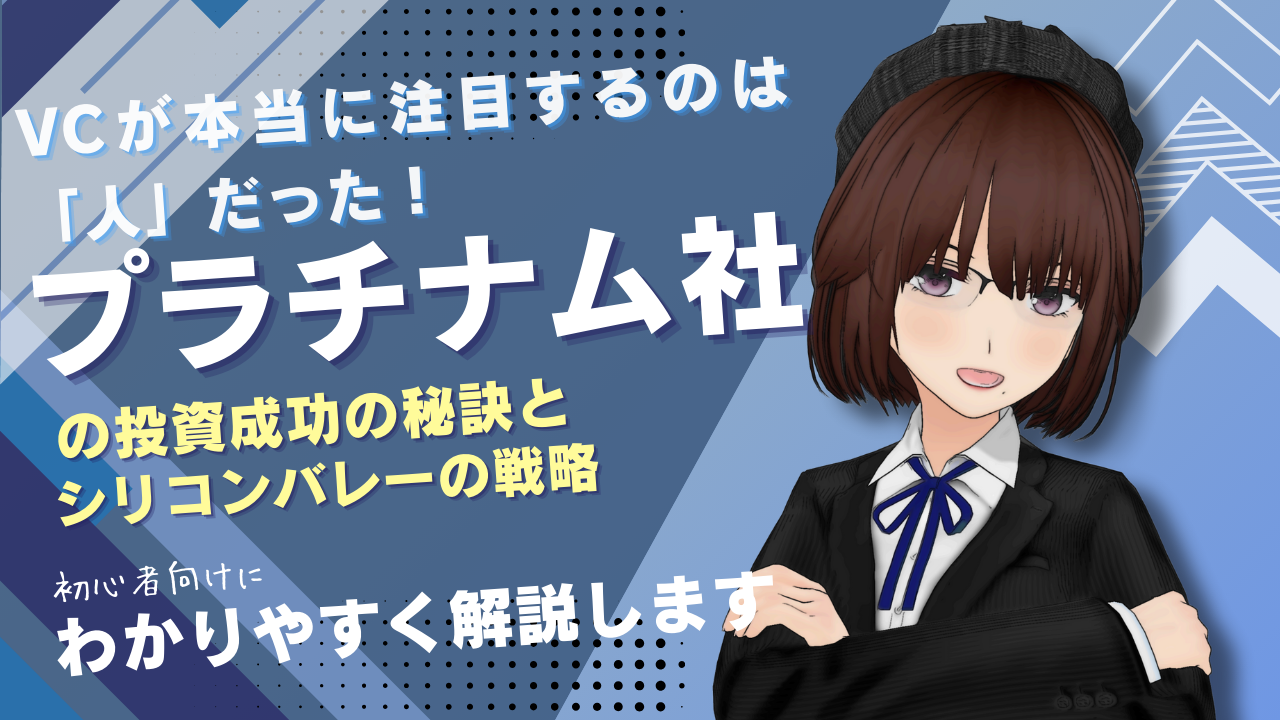
コメント